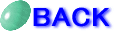平成20年10月14日
五 小 の 風 景 No.7
五日市小学校長
国政 直文
|
公徳心
最近,歩道に植えられているチューリップの花を摘み取ったり,世界遺産に落書きをしたりと,公徳心のなさ,モラルの低下を嘆き,怒る声をよく聞きます。これは,国民全体の公衆道徳の低下を表しています。
では,現在においてのみ,公徳心というのものが特に顕著に低下しているのでしょうか。
このことについて,次のような記事が掲載されていました。(鈴木 勲氏著)
「近代国家として発足した明治時代はどうであったか。明治の思想家西村茂樹は,1900年(明治33)年に小学校訓導を対象にした道徳教育講話の中で,わが国には久しく社会道徳がかけており,公園の桜を折る,神社や仏閣にいたずらで落書きする,汽車の中で席を独占したり物を食って散らかすなどの例を挙げて,公徳心の養成の必要性を述べている。また,戦前はどうであったか。1941(昭和16)年に文部省(当時)が発行した「礼法要項」によると,「社会生活に関する礼法」の中で,公園ではみだりに草木などに手を触れない,車内ではみだりに席を広くとったり脚を前に長く伸ばしたりしない,船車内では飲食に注意し見苦しくないようにし,汚さないようにするなどとうたい,社会生活に関する礼法は国民の品格向上に重要なものと位置づけている。」
この記事を読む限り,100年前から日本人は現在と同じように公徳心に欠けていて,その後もあまり向上していないということなのでしょうか。ということは,なぜ公徳心というものが向上しなかったのか,どういう手段をとれば向上するものなのかということを真剣に考える必要があると思います。
学校においては,まずはその必要性を道徳の授業の中で十分に理解させることが大切であると思います。そして,理解したことを様々な場面で行動させ,評価し,自分の行動を振り返らせ,再度行動ということを繰り返していくことが必要だと考えます。社会見学等で学校外で行動する場合もあります。こういう機会をとらえての指導は効果的だと思います。
先月5年生の社会見学に同行しましたが,非常に事前指導がゆきとどいていました。また,不適切な行動に対しては,その場で適切な指導を教員がしていました。教員が引率していながら何の注意もしないという苦情を新聞の記事で目にすることがありますが,本校の教員の場合はそこの所をきっちりと指導できているので素晴らしいと思います。こうした積み重ねが子ども達の公徳心の育成につながるのだと確信しました。
ただし,学校だけで公徳心の育成をはかることはできません。当然,家庭・地域との連携が重要です。ご家庭でも公徳心の必要性を話していただくと同時に,私たち大人が子ども達に見られて恥ずかしくない行動をとりたいものです。
授業の一風景
今,低学年から順に各クラスの子ども達の授業の様子を見ています。いつの時間に参観するということを言わずにいきなりの授業参観なので,先生達も大変だとは思いますが。そこで気づいたことを一つ紹介します。
それは,ほとんどのクラスで,授業開始のチャイムの合図とともに日直の号令により授業が開始されているということです。こういうことはごく当たり前のことですが,この当たり前のことを当たり前にできるところに教員の指導の徹底と,指導のもと着実に力をつけている子ども達の大きな成長を感じます。
皆さんご存知のように,本校では,今年度,「時間を守る」ということを一つの重点目標にしています。これまで,様々な場面で教職員全員がそういう意識を強く持って取り組んできました。その効果が確実に表れていると思いました。前期は今日で終了です。後期も引き続きご理解ご協力お願いします。