平成21年 2月23日
五 小 の 風 景 No.11
五日市小学校長
国政 直文
|
「だからこそコミュニケーションを」
「梅一輪 一輪ほどの あたたかさ」という服部嵐雪の句のように,まだまだ寒さが厳しいこの頃ですが,少しずつ春を感じるようにもなってきました。本校の中庭の紅梅も咲き誇り,その美しさに春の訪れを感じます。同時に,今年度ももう少しで終わりなんだなということも頭の中をよぎる季節となりました。また,1年間の取組を振り返る時期でもあります。
最近,携帯電話等の通信機器の発達や社会の複雑さにより,コミュニケーション(特に言葉による)が成り立ちにくい状況にあるということから,今年度「コミュニケーション能力の育成」を目標に授業研究を続けてまいりました。この取組が,どれくらい子ども達のコミュニケーション力を育てることにつながったのか,効果的な取組はどんなことだったのか,もっと効果的な取組はなかったのか等,いろいろと省みているところです。
「コミュニケーションはまさに生きる力の根源である。」これは,先月末に実施しました公開授業の講師としてお招きした山本名嘉子先生の講話の中での言葉です。様々な価値観があり,直接的なコミュニケーションをとらなくても不便さを感じないような今そしてこれからの社会においては,先の言葉のようにコミュニケーション(特に言葉を使う)が益々重要になってくると考えられます。
岸見一郎氏の著された本に,男性は火星人で女性は金星人であったという寓話が紹介されています。まさにコミュニケーションの大切さを言い得たものだと思います。その寓話とは,次のようなものです。
ある日,男性が望遠鏡をのぞいていたら美しい女性の姿が目にとまります。彼は思い切って声をかけました。思いがけずデートに応じた彼女とその後もデートを繰り返すようになります。この頃,二人は互いの考え方,感じ方に自分とは異なるものがあるのに気づきます。それはすぐには受け入れることのできないものですが,それでも二人は相手は異星人なのだから,こんなことがあって当然,と話し合うことができました。
やがて惑星空間内でのデートにも飽き,そろそろ落ち着きたいと考えて男性は女性にプロポーズし,めでたく結婚して地球に新居を構えます。
子どもが生まれます。実はこの頃から二人のコミュニケーションはギクシャクし始めます。生まれた子どもは何人でしょうか。そう,地球人です。そして自分たちも地球人だと思い始めるようになります。するとそれまで相手の考え方,感じ方に違和感があっても,相手は自分とは違う異星人だからと許せていたのに,同じ地球人なのになぜ同じように考えないんだろう,感じないんだろう,許せない,ということになったのです。初めはわからなくて当然と思っていて,わからないことを前提に逆にわかろうとする努力をしていたはずなのに・・・・・。
また,オーストリアの精神科医であったアルフレッド・アドラーは,そもそも相手を理解することは不可能であると言っています。つまり,この寓話のよ うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。
うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。
少しでもお互いがわかり合えるためにも,言葉によるコミュニケーションをどんな場でも大切にしていきたいものです。
今年度も残り1ヶ月程となりました。ご協力の程、よろしくお願いします。
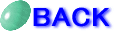
 うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。
うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。
 うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。
うに,わからないと思って付き合うことのほうが,わかり合えると思って付き合うよりはるかに安全だと考えます。だからこそ,相手をわかろうと努力するためには,言葉を使うコミュニケーションが重要であると強調しています。